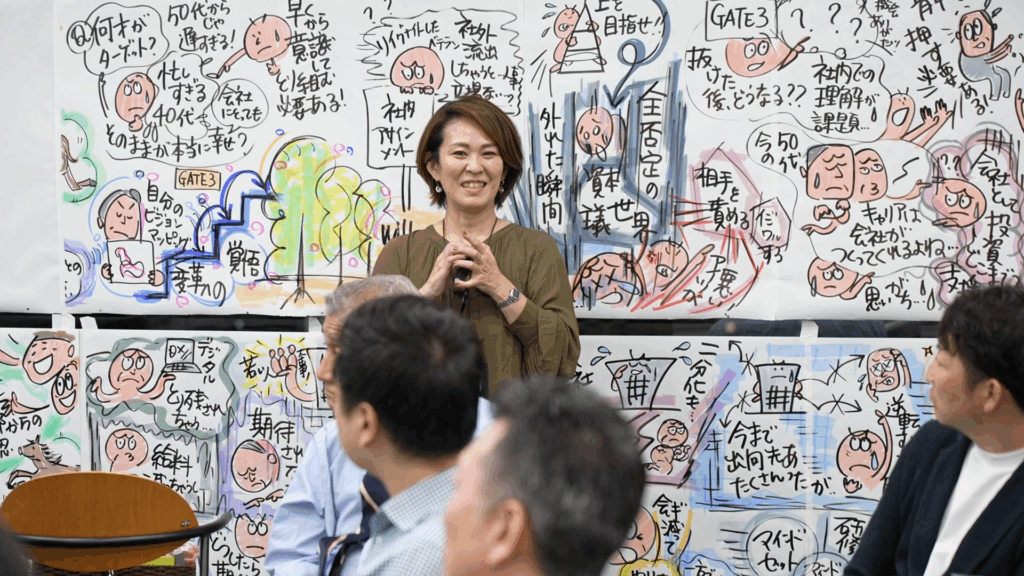質疑応答
質問⑧:本当に成果につながるのか?社内承認が先ではないのか?
ゲスト:
ゲートⅠで語られていた「承認」の考え方、理屈としては非常に納得感があります。ただ正直なところ、「社内に対してすでにネガティブになってしまっている人」が、このプロセスで本当に変われるのか——そこには少し懐疑的な気持ちを持っています。
むしろ、そうした方々こそ、社内での承認体験が欠けているからこそ卑屈になってしまっているのではないかと。そうであれば、社外のプログラムで変化を起こす前に、社内でどこまで承認できるかも重要ではないかと感じました。

Hiro
とても鋭いご指摘です。まさにその通りで、だからこそ私は「一度、お試しでやってみること」に大きな意味があると考えています。
結局のところ、最終的な承認とは「自己承認」でしかないと思うんです。他人の物差しだけでは、自分の人生の納得には至らない。だからこそ、自分自身に矢印を向ける力が必要です。そしてそのためには、一度会社や既存のステークホルダーから自分を切り離して、自分と深く向き合う時間が欠かせません。
ただ、ここで重要なのは、それを「つらく深刻にやる」のではなく、「ピュア「な気持ちで自分を見つめ直す体験にすることです。
たとえば、馬とのふれあいや災害復興の現場など、他者や自然との疑似体験を通じて、自分の「本質的な反応」を観察する。「なぜ自分は人を助けたくなるのか?」「なぜ黙って傍観してしまうのか?」——そうした気づきの積み重ねが、自己承認のきっかけになると考えています。
そして、ただ体験して終わるのではなく、それをグループ内で共有・内省する時間が必要です。その対話の中で、他者の視点からも自分が照らされていくことで、「他者からの承認」と「自分による承認」が繋がっていく。
このプロセスがあることで、はじめて「自分のピュアな部分」が輪郭を持ち、それを「これからの人生のど真ん中に据える」という覚悟につながっていくのだと思います。
ちなみに「自分」という字は、「自らを分ける「と書きますよね。つまり、自分の内側から見ている自分と、他人から見られている自分を分けて考える。その両方の視点を行き来できるようになることが、「自分を見る力」=自己認識力を育てるうえで非常に重要だと思っています。
質問⑨:この研修を「会社が用意する意味」とは何か?
ゲスト:
本プログラムの趣旨や構成は理解しました。ただ、あらためて伺いたいのは、この研修を「会社が用意すること「の意味についてです。単にキャリア研修として外部提供するのではなく、「自社がこのプログラムを社員に提供する意義」について、もう少し解像度を上げて考えたいと思っています。

Hiro
非常に本質的な問いをありがとうございます。
私自身は、これは一言でいえば「会社のブランディングそのもの」だと思っています。
つまり、会社がどんな「覚悟」を持って人と向き合っているのかを示す行為なんですよね。
例えば、何百万円単位の大きな投資を求めるわけではありません。でも、「自社が本気で背中を押す」という姿勢を形にすることは、とても大きな意味を持つと思うんです。
こんなエピソードがあります。ある商社の社員の方が、社内の資格制度に挑戦したのですが、不合格になってしまいました。本人にとってはかなりのショックだったようです。
そんなとき、上司が「モンゴルに行ってみないか」と声をかけた。するとその方は「行きます!」と即答し、実際に参加してこう言ったんです——「最高でした」と。
つまり、「来たこと自体が、自分にとってすでに価値ある経験(自己承認)になっていた」。それを聞いて私は思ったんです。これこそ「かっこいい会社のあり方「なのではないかと。
たとえば早期退職金が17ヶ月分あるとしたら、そのうちの3〜5%を本人に出してもらう、もしくは退職後に返済してもらう仕組みにするなど、やりようはいくらでもあると思っています。重要なのは、どこかのタイミングで「自分事」としてこの機会を捉えること。そして、それを「自分のツール」として再構成していくことなんです。
だからこそ、最初の一歩は会社が支援してもよい。でも最終的には、自分の意志で「そのゲートをくぐる」という姿勢が何よりも大事なんです。
このプログラムの設計においても、最初は受動的な入口から始まり、最終的には「能動的な行動」へと移行していく構造が必要だと考えています。そうでなければ、いつまでも会社が用意し、人事が段取りするだけの研修にとどまってしまう。それでは、本当の意味での変容は起きない。これまでの経験から、強くそう感じています。
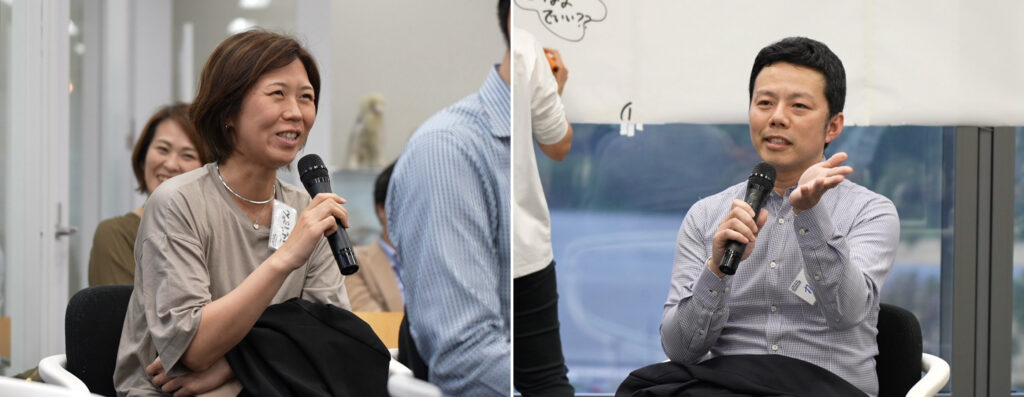
質問⑩:早期退職者たちのその後に学べること。
ゲスト:
私の前職は製薬会社だったのですが、早期退職制度が積極的に活用されていて、いわゆる「手を挙げる」文化がかなり浸透していました。とくにMR職や研究職の社員は、自分の10年後を見据えたときに「このままでは厳しいかもしれない」という危機感を抱いていたようで、MBAや中小企業診断士の取得、ビジネススクールでの学びに自己投資する人が非常に多かった印象です。
辞めた後の彼らと集まって話をすると、「NPOを立ち上げた」「医療コンサルを始めた」など、それぞれが自分の軸を持って楽しそうに働いている姿がありました。社外には「辞めた人たちのコミュニティ」も自然に生まれていて、在籍時には実現しきれなかったけれど、退職後にそれぞれの人生がうまく回り出しているようにも見えました。彼らは皆、自ら手を挙げた。そこにヒントがあるように思います。

Hiro
おっしゃる通りですね。私も、早期退職の制度を「選択肢」として活かし、自ら道を切り拓いていく人たちは、実際にポジティブな変化を遂げていると感じます。そういう意味で、「会社が背中を押す仕組み」として早期退職や自立支援を用意するのは意義あることです。
一方で、私が危惧しているのは、「なんとなく残って、なんとなく動かない」ままの状態で時間が過ぎてしまう人たちの存在です。とくに、自分では動かずに「評論家」のようになってしまい、いざとなるとアクションを起こせない——そんな姿をよく見かけます。
そのような人たちに対して、どう「自分ごと」として物事を捉えてもらうかが、今後の大きな課題だと感じています。
だからこそ、Reignitionのようなプログラムでは、ただ機会を提供するだけでなく、「自らの意思で火を灯し、動く」ことを促す導線をしっかり設計していく必要があると考えています。
質問⑪:「手を挙げる人」をどう見極めるか?
ゲスト:
「もう少しで動き出しそうな人たちに、どう「声をかけるか」という仕組みづくりが鍵になると感じました。全員が対象というわけにはいかない。だからこそ、「会社からの声かけ」と「本人からの自発的な手挙げ」の両輪が必要だと思います。
たとえば、「会社で働き続けたい」と考える人には、「じゃあどう貢献してくれますか?」と問えるような選択肢も設計しておく。逆に、「何かやりたいなら、自分で提案してみてよ」というような、プレゼン機会と承認を紐づける形もアリだと思います。
こうすることで、会社としても「一部は支援するけれど、その分しっかりやってね」というコストと期待のバランスを取った設計ができる。その際に、本人が社内で仲間を見つけられるような「コミュニティ」の存在があれば、さらに機能しやすくなるかもしれません。
また、たとえ取り組みの内容が直接的に会社に関係していなかったとしても、「一部を会社として応援できる」と思えれば、「いってらっしゃい」と送り出しやすくなる。
すべてが「三方よし「にはならないかもしれませんが、「会社が投資してよかった」とみんなが実感できるような設計がされていれば、再現性のある成功につながるのではないかと思います。

Hiro
ありがとうございます。少し抽象的になりますが、やはり「良いエネルギーは、良いエネルギーの場からしか生まれない」というのは本質だと思っています。逆に、ネガティブな空気に引きずられると、どうしても全体が「抑え込みモード」になってしまう。そうならないように、ポジティブな循環の最初の一歩をつくるのが、やはり「会社の責任」ではないかと私は思います。
本人が自ら手を挙げること、そして会社もそれを受け止めること——そのマッチングが起きれば、エネルギーの好循環が生まれる。そうすれば、「もっと貢献したい」「こんな形で会社にコミットしたい」と自発的な提案も出てきて、自然と一歩前に進めるのではないでしょうか。
いままでの状態だと、「私は頑張ってきたのに、なぜ何も与えられないのか?」というような、ネガティブなループに入りやすい状況があると思うんです。
だからこそ、「ここから先の人生を、自分の意思でつくっていく」——そんな覚悟と投資の機会を会社がつくってあげることができれば、それは会社にとっても本人にとっても価値あるものになるのではないかと考えています。

質問⑫:そもそもシニア層へ投資する理由は?
ゲスト:
シニア人材の「2:6:2」のどこに投資するのが一番効果的なのかを考えていました。ただそれ以前に、会社としてはシニア層に対しては「モチベーションの維持」程度の関わりにとどまり、積極的な投資はあまりできていないのが実情です。
シニア層に向けたどんなに優れたプログラムであっても、これだ!と思えるものはなかなかなく、イメージしづらいのが本音です。そもそもシニア層に対して、会社として何を期待すればよいのでしょうか。

Hiro
シニア人材の扱われ方というのは、実はその下の世代にも大きな影響を与える要素だと思います。若手がそれを見て「将来あんなふうに扱われるなら嫌だな」と感じてしまえば、ネガティブなスパイラルを生む可能性すらある。
ところが、多くの会社ではそこの投資の優先順位は高くない。「なるべくならそのまま静かに…」「早期退職で整理を」——そんなムードが無意識のうちに醸成されてしまっている。
でも、それって誰も得しないんですよね。シニア層が意欲を失い、実質的に「誰も働いていない」状態になってしまう。だからこそ、今回のような仕掛けは、「状況を変えるための一手」として有効だと考えています。
正直なところ、私たちも「2:6:2」のどの層をターゲットにするかは、厳密には決めていません。大事なのは、「この人は、もしかしたら火がつくかもしれない」と期待できる一人ひとりを丁寧に見出していくことなんじゃないかと。
主観的な「インプレッション」に基づいて、あえてピックアップする——それが、このプログラムにおけるリアルな対象設定の出発点になるのではないかと考えています。
質問⑬:このプログラムは「美しい出口戦略」になり得るのか?
ゲスト:
会社としてこのプログラムに投資する意義は何か—と考えたとき、これは「とても美しい出口戦略」になるのではないかと感じました。
一般的な研修では、「行動変容が起こるのが20%」「継続できるのがそのうちの20%」とも言われます。つまり、100人のうち本当に変容し続けるのはわずか4人ほどということになります。
このプログラムによって「内発的動機付け」がなされたとしても、それを社内で継続できる環境がなければ、結局アウトプットにはつながらない。
ですから、社内アサインメントとその後の「継続支援の仕組み」がセットになっていなければ、投資対効果を得るのは難しいと思います。また、ベテラン層では、「上司との相性」が影響してモチベーションが下がってしまうケースも多くあり、少し配置を変えるだけで、再び輝きを取り戻すこともある。
だからこそ、このプログラムを4%の人材には「動機付け+適切な配置転換」を提供するもので、それ以外の人に対しては「美しい出口戦略」として捉えた方が現実的に機能しそうだと思って見ていました。

Hiro
ありがとうございます。非常に適切なご指摘だと思います。理想を言えば、社内で継続的な変化が生まれ、良い上司とのマッチングも実現することがベストです。ですが、現実的には、社内のしがらみやプライドなどが邪魔をして、思うように動けない・受け入れられないというケースも少なくありません。
そういったときにこそ、外部のプログラムを活用することが突破口になるのではないかと思って、今回の構想を考えました。
今後のアサインメントについても、やはり最も効果的なのは「本人に自ら描かせること」だと思っています。自分の未来や役割を「自分で設計する「ことで、初めて納得感のある行動に繋がる。だからこそ、「変わる前に描く」ことが何よりも重要だと考えています。
その点についても、ぜひまたご意見をいただけるとうれしいです。

質問⑭:参加対象者の選び方と「波及効果」について
ゲスト:
先ほど議論にあった「ターゲット」についてですが、たとえば「この人が行ったら変わるかもしれない」と期待される方を選ぶという視点もあると思います。一方で、現実として企業が50代社員に予算を投じることへのハードルは依然として高い。
だからこそ、参加人数は絞った上で、インパクトが出る設計が必要だと考えています。つまり、「あの人が変わったのならすごいね」「あの人の変化が社内に広がるなら価値があるね」といった、周囲に波及していく「象徴的な変化」が生まれるような設計にしたい。
そうした「社内に影響を及ぼす人」を起点にプログラムが浸透していけば、経営側としてもコスト投下の納得感が高まるのではと感じました。その点も踏まえて、プログラムとどうつなげていくかが鍵だと思っています。

Hiro
まさにおっしゃる通りで、「あの人が変わったなら本物だよね」という声が上がるのは、僕たちにとっても本望です。過去にIWNCのプログラムを受けた方から「IWNCの人たちは心を削って伴走する」と言われたこともありました(笑)が、それぐらい深く、真摯に向き合うスタイルであることは確かです。
ただ一方で、最終的に「変わるかどうか」は私たちがコントロールできる領域ではないというのも事実です。あくまでも私たちにできるのは、伴走し、刺激を与え、気づきを促す場を整えることです。
「教えられたからやる」のではなく、自分で気づいて動けるかどうかがカギなんです。たとえば「承認」という行為も、「承認しなさい」と指示して成立するものではない。それよりも、本人が自ら承認を実感できるような刺激や関係性をどれだけ周囲にちりばめられるか—そこにかかっていると感じています。
ミチルも何か話してくれる?

ミチル
先ほどのご意見を聞きながら、私自身も強く共感していました。「この人なら変わるかも」と期待されて声をかけることは理想的だと思いますし、一方で、「誰でも変われる可能性はある」という視点も大事だと感じています。だからこそ、「誰にでも手を挙げるチャンスがある」プログラムの設計も、あっていいのではないでしょうか。
たとえば、外にチャレンジしたい人、中で頑張りたい人、それぞれいると思いますが、共通して必要なのは「ウィル」。そのウィルを持って自ら手を挙げた人をきちんと受け止められるようなプログラムが大切だと感じています。
私はコーチングをしているのですが、いま一定年齢以上の方々がスクールに通ってコーチングを学ぶケースが非常に多いんです。100万円単位の自己投資をしてでも「何かを変えたい」と思っている。それは、「自分自身にまだ期待している」からなんですよね。
ただ、中には「資格を取ること」が目的になってしまう人もいる。でも、資格だけで何かが劇的に変わるかというと、そんなことはない。だからこそ、「もっと本質的な何かがあるよ」ということを伝える場や機会が必要だと思っています。
そしてこれは、私自身も年齢を重ねて感じることでもあるのですが、今の日本社会全体が高齢化している中で、このテーマは一部の人に限ったことではなく、むしろ多くの人に関係する話題なんだと改めて思いました。