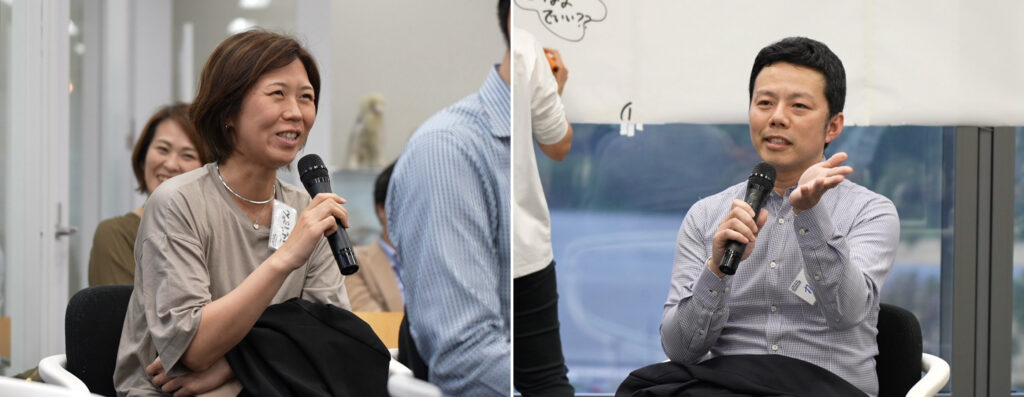質疑応答
質問①:プログラムの対象年齢は?
ゲスト:
非常に興味深いお話でした。ひとつ確認したいのですが、今回のプログラムで想定されている対象年齢はどのくらいをイメージされていますか?

Hiro
これは非常に重要な論点でして、企業によって「シニア人材」と定義される年齢はまちまちです。たとえば、シリコンバレーでは「30歳以上はシニア」という感覚もあるくらいですから(笑)、一概には言えません。
ただ、日本企業においては、たとえば定年を53〜55歳に設定しているケースもありますし、その前後を意識していただいてもよいかと思います。
また、よく言われる「2:6:2」のアップサイド層のうち、一歩踏み出せば変わるかもしれない層がどの年代に分布しているかを見極めるのも、一つの切り口になるかもしれません。
質問②:むしろ40代の「多忙層」こそ早期介入が必要では?
ゲスト:
実は私の担当領域でも、50代のキャリア研修は比較的前向きな雰囲気があります。一方で、40代は目の前の業務に追われ、自分と向き合う余裕すらなくなっている方が多い印象です。その結果、50歳になって初めて立ち止まっても、すでに手遅れというケースがある。だからこそ、「40代で気づきを与える機会を持たせるべきでは?」と思いました。

Hiro
まさにその通りだと思います。そもそも「年齢」が意味するものは、健康状態やモチベーションの個人差を無視して一律に語ることが難しい時代です。
ただ、今の40代が抱えている「猛烈な多忙さ」と「内省の喪失」は、キャリアの連続性や非連続性を考えるうえで、大きな断絶を生みかねないとも感じています。
その意味で、40代をターニングポイントとした早期の介入は、今後重要になるはずです。

質問③:社内アサインメントと再着火はセットで機能する?
ゲスト:
「Reignite」で自己の軸や武器が明確になったとしても、それが実際に活かされる場が社内に用意されていなければ、意味を持たないのではないかと感じています。限られた人数でもいいので、アセスメントとアサインメントをセットで取り組むべきではないでしょうか?

Hiro
ご指摘の通りです。
ただ、実情としては、多くの企業において「ポジションの空きが少ない」「なるべく若手に譲ってほしい」といった声もあり、必ずしもアサインメントの確保が簡単ではないのも事実です。
とはいえ、そこで「社内」「副業」「地域貢献」など、いくつかの選択肢を本人が持てる状態にしておくことが重要だと思っています。
重要なのは、会社が「キャリアカウンセリング的に提示する」だけでなく、本人の中に火が灯っていることです。「こう生きたい」「こう働きたい」という内発的な意志が芽生えていれば、たとえ環境に制約があっても、適切な選択ができるようになります。
その意味でも、「Reignite」は、制度でキャリアを導くのではなく、本人が人生のハンドルを再び握る支援でありたいと考えています。
質問④:辞める人が増えたら会社が困るのでは?
ゲスト:
個人的にはこのコンセプトに非常に共感しています。ただ、本人に火がついた結果、「独立しました」となった場合、企業側としては少し複雑な気持ちになるというのも事実かなと感じています。

Hiro
そのご懸念は非常によくわかります。ただ、私たちの経験では、本当に自己変革に向き合える人というのは、むしろ社内でもう一度活躍する余地があるケースが多いんです。
私たちが関わってきた組織の中の「スーパーエース級」の方々の中にも、「会社がダメ」「仕組みが古い」と外部要因を理由に語る方は少なくありません。
でもそういう方には、「ではあなた自身はどう変わるつもりですか?」という問いを投げかけます。本質的な変化は、会社や制度のせいにせず、「自分に矢印を向けること」からしか始まらないと思うんです。
たとえば、モンゴル研修では、参加者に「覚悟」を求めます。それが正解かどうかは分からなくても、まずは自分に責任を引き寄せる経験をしてもらう。それこそが、Reigniteの本質だと考えています。
質問⑤:会社がこの研修を導入する意味付けは?
ゲスト:
このプログラムを導入すると、目覚めた人が一定数現れるとは思うのですが、会社としてこのプログラムをどう位置づけて受け止めるか、そしてどう社内に説明していくか……まだ解が見えていません。

Hiro
とても率直で大切なご意見、ありがとうございます。まず、「セカンドキャリア」という言葉自体に、私も強い違和感があります。聞く側としても、「セカンドって、会社都合で次を用意されているだけじゃないのか?」と感じてしまうんですよね。
結局のところ、どんな制度や仕組みも「会社都合「であるという事実は避けられません。
でもその中で、本人が「もう一度、自分の人生を自分の意志で歩もう」と思える瞬間が訪れたら、それは大きな価値だと私は思っています。
そしてもう一つ重要なのは、「他流」でやること。
社内でのキャリア支援は、どうしても社内の評価軸に引っ張られがちです。
でも他社の人たちと出会い、似たような境遇や志を持つ仲間と交わることで、
「自分にもまだ価値がある」「誰かの役に立てる」という「効力感」が芽生える。
この効力感こそが、人の変化をドライブする最も大きなエネルギーだと思っています。
そのためには、社内で頑張り直すというよりも、新しいコミュニティの中でわちゃわちゃしながら、自分らしい価値を見出していくプロセスが必要なんだと思います。
質問⑥:この研修を「会社が用意する意味」とは何か?
ゲスト:
本プログラムの趣旨や構成は理解しました。ただ、あらためて伺いたいのは、この研修を「会社が用意すること」の意味についてです。単にキャリア研修として外部提供するのではなく、「自社がこのプログラムを社員に提供する意義」について、もう少し解像度を上げて考えたいと思っています。

Hiro
非常に本質的な問いをありがとうございます。
私自身は、これは一言でいえば「会社のブランディングそのもの」だと思っています。
つまり、会社がどんな「覚悟」を持って人と向き合っているのかを示す行為なんですよね。
例えば、何百万円単位の大きな投資を求めるわけではありません。でも、「自社が本気で背中を押す」という姿勢を形にすることは、とても大きな意味を持つと思うんです。
こんなエピソードがあります。ある商社の社員の方が、社内の資格制度に挑戦したのですが、不合格になってしまいました。本人にとってはかなりのショックだったようです。
そんなとき、上司が「モンゴルに行ってみないか」と声をかけた。するとその方は「行きます!」と即答し、実際に参加してこう言ったんです——「最高でした」と。
つまり、「来たこと自体が、自分にとってすでに価値ある経験(自己承認)になっていた」。それを聞いて私は思ったんです。これこそ「かっこいい会社のあり方「なのではないかと。
たとえば早期退職金が17ヶ月分あるとしたら、そのうちの3〜5%を本人に出してもらう、もしくは退職後に返済してもらう仕組みにするなど、やりようはいくらでもあると思っています。重要なのは、どこかのタイミングで「自分事」としてこの機会を捉えること。そして、それを「自分のツール」として再構成していくことなんです。
だからこそ、最初の一歩は会社が支援してもよい。でも最終的には、自分の意志で「そのゲートをくぐる」という姿勢が何よりも大事なんです。
このプログラムの設計においても、最初は受動的な入口から始まり、最終的には「能動的な行動」へと移行していく構造が必要だと考えています。そうでなければ、いつまでも会社が用意し、人事が段取りするだけの研修にとどまってしまう。それでは、本当の意味での変容は起きない。これまでの経験から、強くそう感じています。
質問⑦:そもそもシニア層へ投資する理由は?
ゲスト:
シニア人材の「2:6:2」のどこに投資するのが一番効果的なのかを考えていました。ただそれ以前に、会社としてはシニア層に対しては「モチベーションの維持」程度の関わりにとどまり、積極的な投資はあまりできていないのが実情です。
シニア層に向けたどんなに優れたプログラムであっても、これだ!と思えるものはなかなかなく、イメージしづらいのが本音です。そもそもシニア層に対して、会社として何を期待すればよいのでしょうか。

Hiro
シニア人材の扱われ方というのは、実はその下の世代にも大きな影響を与える要素だと思います。若手がそれを見て「将来あんなふうに扱われるなら嫌だな」と感じてしまえば、ネガティブなスパイラルを生む可能性すらある。
ところが、多くの会社ではそこの投資の優先順位は高くない。「なるべくならそのまま静かに…」「早期退職で整理を」——そんなムードが無意識のうちに醸成されてしまっている。
でも、それって誰も得しないんですよね。シニア層が意欲を失い、実質的に「誰も働いていない」状態になってしまう。だからこそ、今回のような仕掛けは、「状況を変えるための一手」として有効だと考えています。
正直なところ、私たちも「2:6:2」のどの層をターゲットにするかは、厳密には決めていません。大事なのは、「この人は、もしかしたら火がつくかもしれない」と期待できる一人ひとりを丁寧に見出していくことなんじゃないかと。
主観的な「インプレッション」に基づいて、あえてピックアップする——それが、このプログラムにおけるリアルな対象設定の出発点になるのではないかと考えています。