イベント名:
シニア社員のセカンドキャリアを考える共創ミーティング
日時:
2025年3月28日(金)17:30〜
会場:
Future Center Tokyo(IWNC本社)
参加者:
大手企業人事部門責任者、人材開発・組織開発担当者など
イントロダクション
多くの企業がシニア社員の活性化に取り組む中で、制度設計や支援策の整備に加え、いま注目されているのは「本人の意識変革」にどう火をつけるかという問いです。特に、50代以上で役職を離れた社員が、自身の誇りや意欲を見失い、現状維持を望む傾向が強まる中で、「いかにして再び自ら動き出す状態へと導くか」が、日本企業にとって喫緊の課題となっています。
こうした状況を踏まえ、IWNCは本共創ミーティングを開催。「制度では動かない世代」に対して、どのようなアプローチで「再着火」を図ることができるのか。各社の事例を共有しながら、対話を通じて新たな視点を探りました。
本レポートでは、当日のプレゼンテーションやディスカッションから見えてきた、シニア社員の可能性と再活性化に向けた鍵となる視座をお届けします。
シニア社員とは?
本共創ミーティングにおける「シニア社員」とは、50代以上で、組織の根幹的な役割から離れた人材を指します。必ずしも定年を迎えたわけではなく、役職定年やキャリアの転換点にある方々を指します。
シニア社員のことを共に考える対話の場

HIRO
こんにちは。IWNCのHIROと申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
今日は僕から何かを教えるとか、知識を伝えるとか、「これ買ってください」みたいな話ではまったくありません。むしろ、皆さんと一緒に考えたい、というのが趣旨です。
今の日本社会で言われている「社会課題」の一つに切り込みます。いつのまにか重くなった「上の世代(シニア社員)」に対して、どのように向き合い、どんな政策や戦略を取るべきか。会社として「こうあるべきだ」「こうしなければならない」と思いながらも、「それって本当に正しいのか?」「今の社会にとって有効なのか?」と、悩みながら進めておられる方も多いのではないでしょうか。
今日は私たちからも「こういうアプローチがあるんじゃないか」というご提案はさせていただきますが、それ以上に「いや、うちはこういうことやってます」みたいなことも含めて、ざっくばらんにディスカッションできる場になればいいなと思っています。
今日の場でお互いの情報も共有し合い、「あ、そういうことやってるんだ!」と刺激を受け合えたらいいなと思っています。「その話は正しいのか?」「いや、それは違うだろう」と否定することなく、フラットに対話できる環境をつくりたい。
途中でカットインしていただいても構いませんし、後半には皆さんにもいろいろ質問させていただきますので、ぜひ活発にご参加いただけたらうれしいです。あ、1人ご紹介するのを忘れていました(笑)。当社の会長の八木Gです。

八木G
皆さんの会社にも、ちょっと「コケの生えたような人」っていませんか?(笑)でも、そういう人を「コケにして終わり」にせず、「元気にしていこう」っていうのはとても大事だと思うんです(笑)。
私は今年70歳になりますが、人生はまだまだ続いていきます。70でも、80になっても、人は成長し続けられる。だからこそ、「定年退職したら夫婦で海外旅行」みたいな話が理想のように聞こえますが、実際には1年くらいで飽きちゃうものです。やっぱりその先に「やること」がないと、人生はつまらない。
私は60を過ぎてから起業しました。「まだやりたいことがある」と思って始めたら、たまたまIWNCという素晴らしいパートナーに恵まれ、一緒に仕事をさせてもらうようになった。そうすると、不思議と「炎」が消えないんです。
だから、「社内で炎が消えかかっている人」に対して、「社内だけでなんとかしよう」と思うのではなく、もっと広い視点で、「人生そのものをどう生きていくか」を考えることが、結果的に社内でも元気に働いてもらうことにつながる。そう信じています。
年齢は関係ありません。皆さんと一緒に、そんな社会をつくっていけたらと思っています。本日はご参加いただき、本当にありがとうございます。
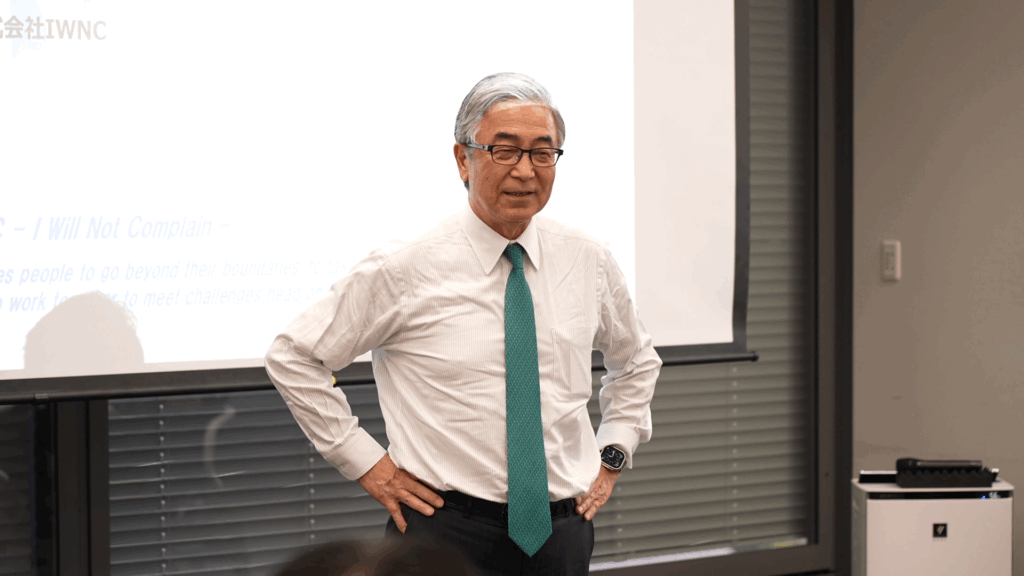
Aさん(食品メーカー)
弊社では60歳を過ぎても定年再雇用で働き続けたい人が働ける制度を整えています。給与体系についても、パフォーマンスを発揮している方については報酬を維持する形を取っています。ただし、社内ではデジタルの進展により、従来のスキルだけでは価値を出し続けることが難しくなってきており、若手や中堅社員の成長を阻害しないためにも、適切な新陳代謝を考えていく必要があると感じています。
Bさん(小売業)
弊社も役職定年はありませんが、60歳以降の再雇用にあたっては、賃金が役職に応じて見直される制度になっています。活躍の場はある一方で、デジタル人材の育成やDX推進においては、なかなか手を挙げるシニア層が少なく、今後の課題と捉えています。
Cさん(不動産)
人材開発部としてシニア層のキャリア研修などに携わっています。不動産業界では、営業経験豊富なシニア人材が他社に移ってしまうケースもあり、待遇や制度面での差が影響しています。社外に出ていくことが必ずしも悪いことではないものの、自社にとって貴重な人材が流出してしまうのは惜しいと感じています。
Dさん(人材教育)
弊社は社長とパートナーで構成されている少数精鋭の組織です。ここ数年、大手企業のシニア活性化支援に取り組んできました。その中で重要だと感じたのは、本人がどこかの組織やコミュニティで『期待される』こと。会社以外でも期待をかけられる場を持つことで、本人のやる気や貢献意欲が高まるのではと考えています。
Eさん(広告制作)
広告業という特性上、若い感性が求められ、45歳くらいから早めに次のステップを考える文化があります。そのため、副業や外部の活動を推奨していますが、自発的に動く人とそうでない人の差があり、支援のあり方が課題です。
Fさん(広告代理店)
今年10月で60歳になります。私自身、成長意欲がある人たちの活かし方に課題を感じていて、会社が成長実感や貢献実感を与えられないと、モチベーションの高い人でも社外へ舵を切ってしまうことがあると感じています。人生のピークは常にこれからだと信じていますが、それを会社として支えることの重要性を痛感しています。
Gさん(小売業)
弊社には多様な職種があり、社内異動も頻繁なため、専門性が育ちにくい構造になっています。その結果、年齢を重ねた社員が『潰しが効かない』と感じ、社内にしがみつこうとする傾向があります。本音としては、社外への視野を持ち、早めに外に出ていってほしいという思いもありますが、思うように手が上がらないという課題があります。
Hさん(重工業)
当社は伝統的な企業で年功序列の文化が強く、シニア社員を処遇変更したくても、本人や上司の心理的ハードルが高く、うまくいかないことが多いです。会社としては水素事業など新しい領域にも取り組んでいますが、活性化している層とマンネリ化している層の二極化が進んでおり、変革に悩んでいるところです。
Iさん(医療機器)
60歳になり、再雇用制度の中で自由な時間が増え、自分のやりたかったことができるようになって面白く感じています。過去には50代向けの研修などを企画しており、自身もキャリアアドバイザーとしてシニア層の活性化支援に携わっています。ただ、年収差の問題から、他社に流出する優秀な人材もおり、これも大きな課題です。
Jさん(メガバンク)
ミドル・シニア向けのキャリア研修を担当しています。銀行では役職定年制度や出向制度があり、40代後半からキャリア意識を持たせる教育を行っています。制度改革も進めており、今後は役職定年の撤廃と併せて、実力主義で若手を登用する流れになる中、シニア層の活躍の場をどう広げていくかが大きな課題です。
Kさん(メガバンク)
銀行では50代前半で外部に出す人事制度がシステマティックに運用されており、枯れていく人材を見なくて済むような側面がありました。しかし外部のニーズが減少し、社内でもシニア人材を活かす必要性が増しています。これまで見なかった層と向き合う必要が出てきたことで、難しさを感じています。
Lさん(金融)
シニア活用は数年前からの課題で、キャリア再考の機会やマインドチェンジ研修を重視してきました。ただ、研修の成果に疑問を感じることもあり、このディスカッションに参加することで、本当に必要な支援のあり方を見極めたいと考えています。
M(広告制作)
弊社では40代中盤でキャリアのピークを迎える構造があり、60代以上の社員が今後5倍に増える見込みです。シニア社員が自らのキャリアを見つめ直す機会を設けるため、外部プログラムへの参加を検討していますが、費用対効果や本人の意欲の問題もあり、悩んでいます。
Nさん(金融)
評価や異動を担当しています。職位定年を迎えた元管理職が部下になることで、新任管理職が扱いづらさを感じるという声があり、課題となっています。現在、社内には何をさせたらいいのか分からないシニア社員が多く、その活かし方が大きなテーマになっています。
Oさん(金融)
当社では社内の半数を占める営業職において、53〜55歳で職位定年を迎えた後のキャリアが課題です。最近は金融教育や社外リスキリングの機会を提供し、実務や教育分野での活躍を促進しています。役職経験者の実務分担や評価の仕組みを通じて、活用の幅を広げていきたいと考えています。
Pさん(不動産)
以前は再開発部門におり、経験豊富なシニア社員に地権者交渉を任せるチームを編成していましたが、作業面で若手への依存が強く、活用に課題がありました。人事部に異動してからは、定年延長により今後さらに多くのシニア社員が残ることを見据え、組織としての対応策を模索しています。

HIRO
それぞれの皆さんが、本当に「真ん中の課題感」を語ってくださっているなと感じています。やはりこういったテーマに明確な正解はありませんし、「これが正解です」というようなものはないと思います。
それでも、今日この場で何かしらの方向性や、これからのためのヒント、あるいはどう仕掛けていくのかといった感覚を少しでも持ち帰っていただけたら、それだけでも十分に意義があったのではないかと、私は思っています。



